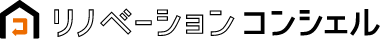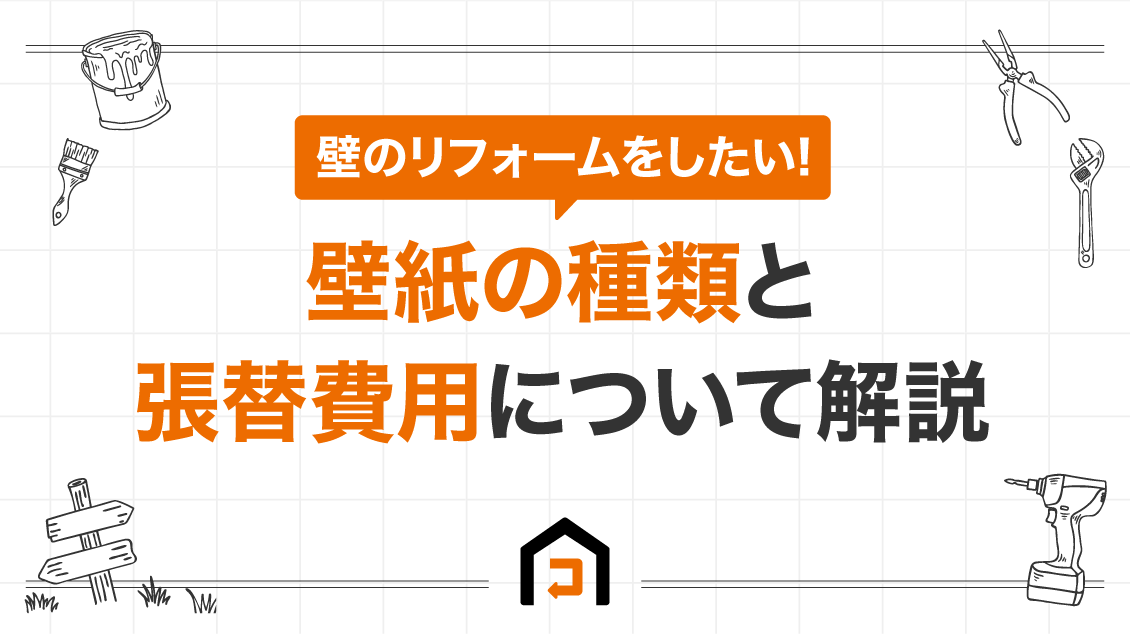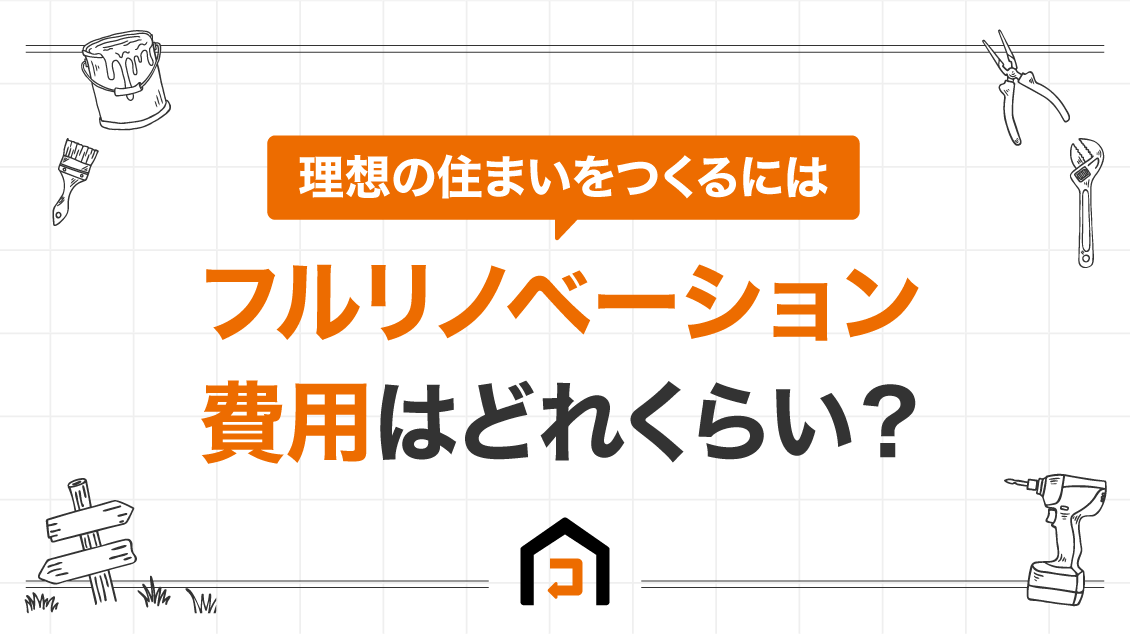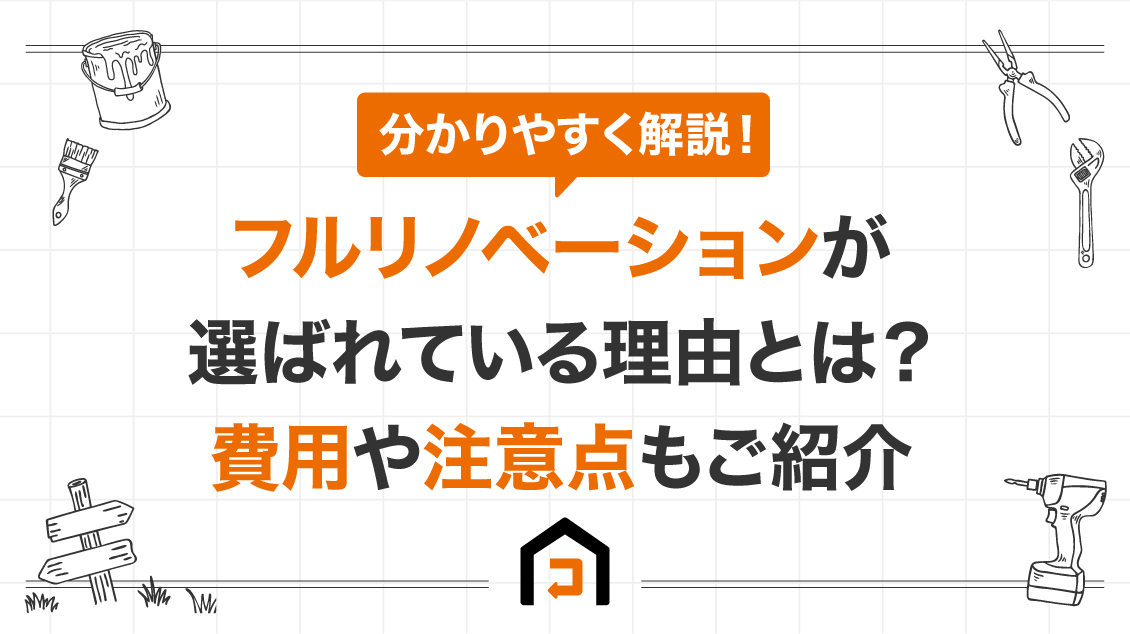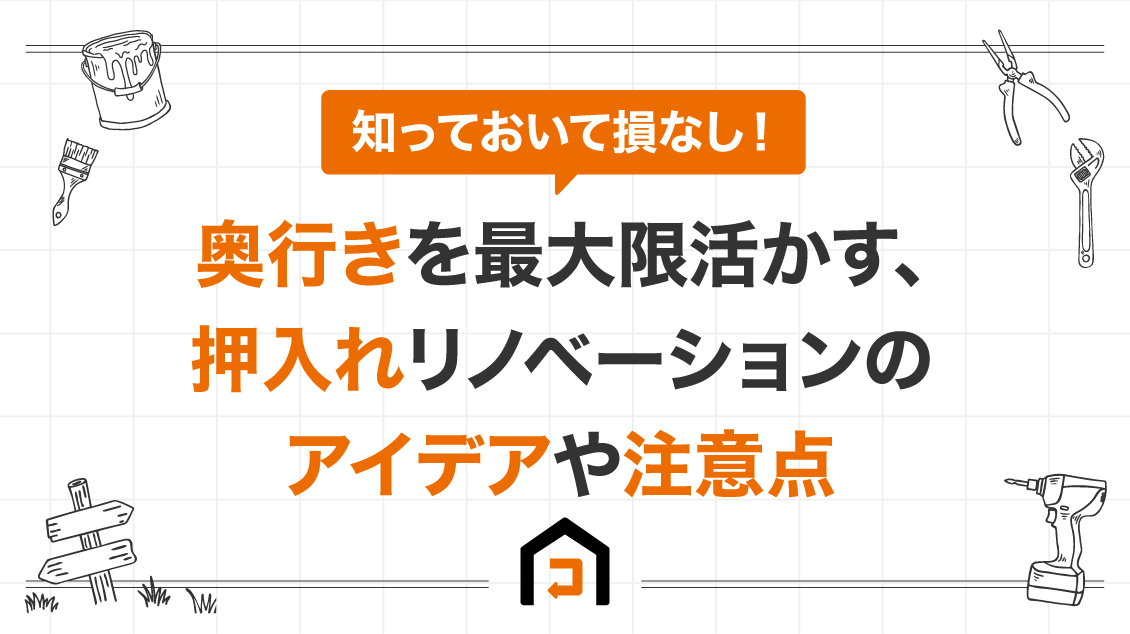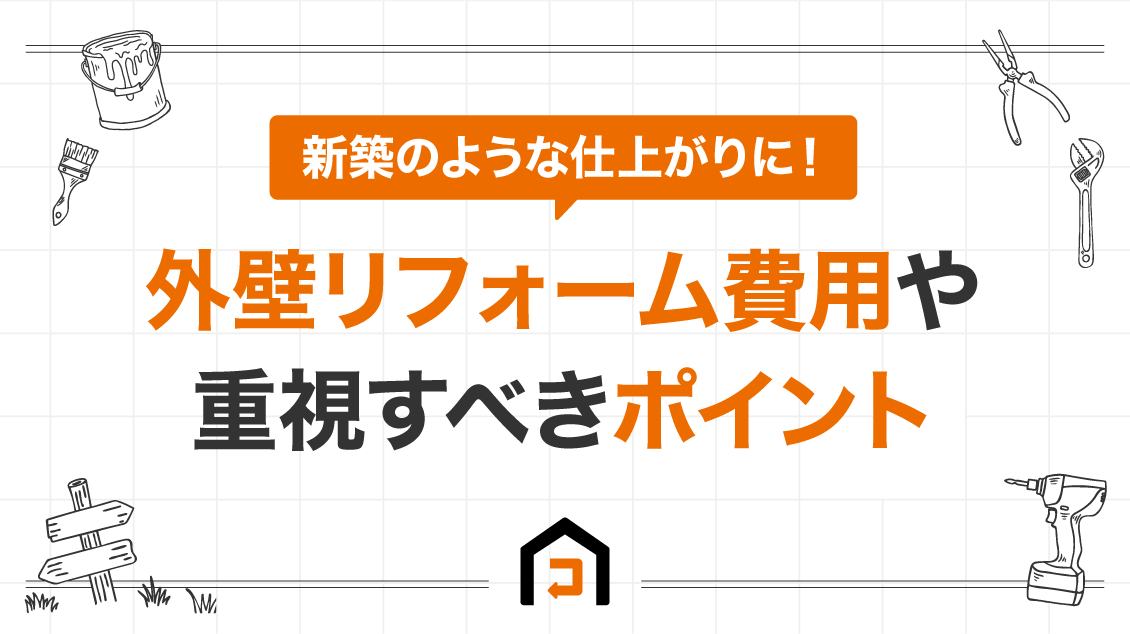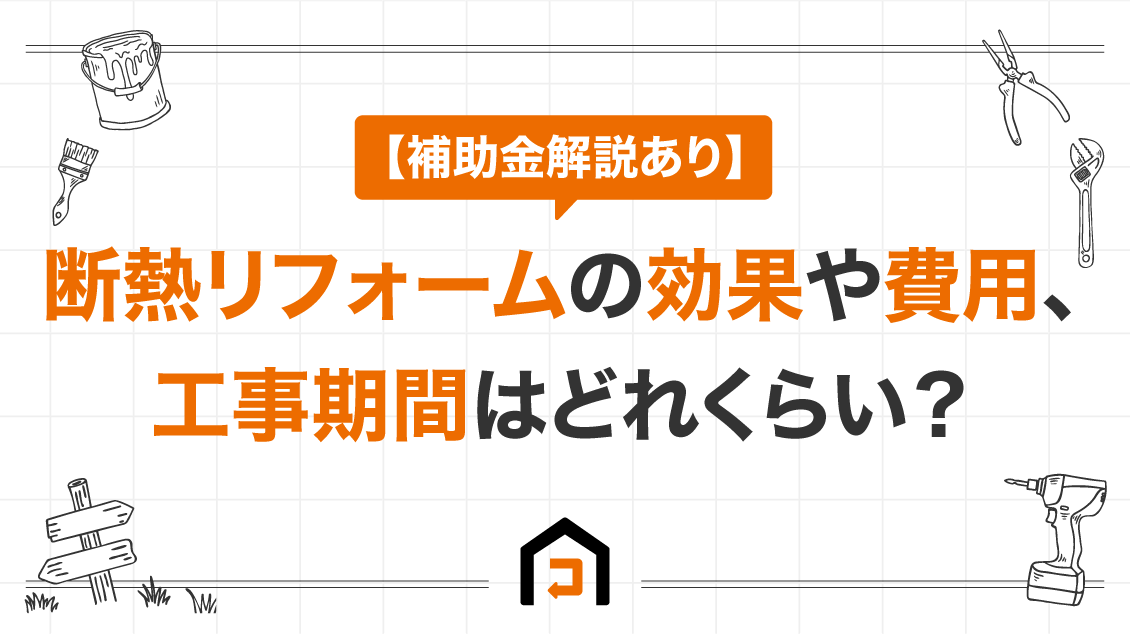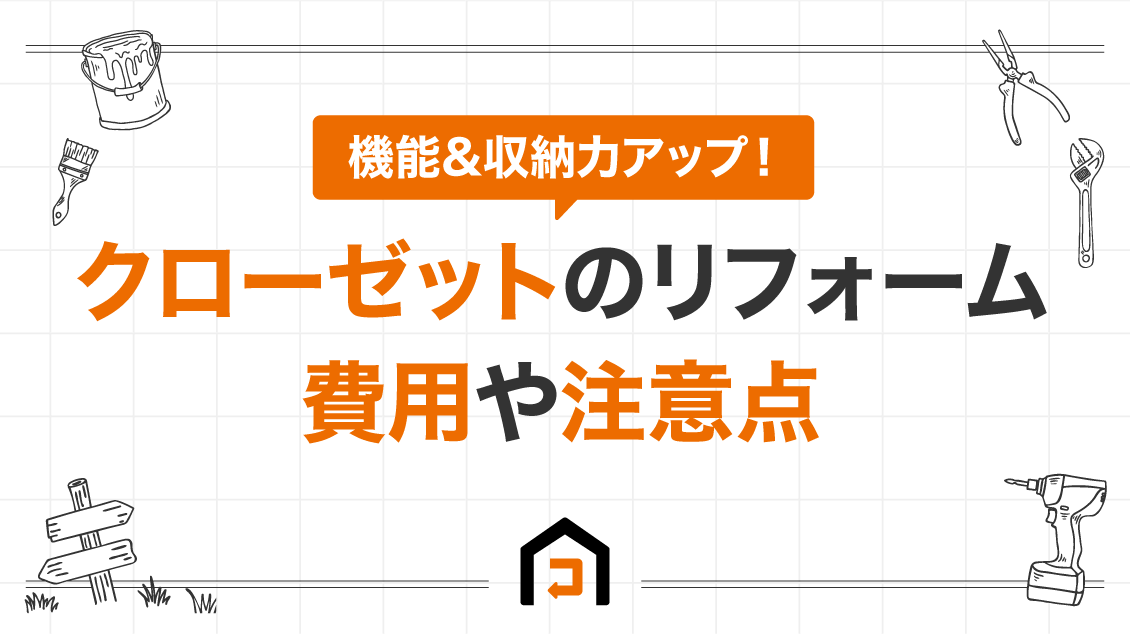壁紙の選び方
壁紙は室内の大部分を占めるため、印象を大きく変えるアイテムです。壁紙を選ぶときは失敗しなくて済むように、様々な観点から選ぶことが必要です。壁紙を選ぶ観点として、素材や機能性、色があります。
素材から選ぶ
壁紙は日本の場合、ほとんどの住宅でビニールクロスが使われます。ビニールクロスが安価で水にも強いからです。しかし、素材にも紙や布など様々な種類があり、素材が違うだけで部屋の雰囲気も変わります。
| 素材 | 概要 |
|---|---|
| ビニールクロス | 塩化ビニール樹脂のビニールシートに紙を裏打ちした壁紙です。壁紙のなかではもっとも安価で多く使われています。 |
| 織物クロス | レーヨンや絹、麻などの布から作られた壁紙です。水や汚れ、埃に弱いですが、織物特有の落ち着いた雰囲気を出すことができます。 |
| 紙クロス | 洋風の紙や和紙などを使ったものがあります。水や油に弱いですが、吸湿効果があります。 |
| オレフィンクロス | ポリエチレンやポリプロピレンなどを原料とした壁紙です。焼却時に有害物質が発生しないため環境に優しいです。水拭きが可能で汚れにも強いのが特徴です。 |
| 木質系クロス | 木を薄くカットして紙に裏打ちした壁紙です。木材を原料としているため、水に弱く拭き掃除ができないのが欠点ですが調湿効果があります。アクセントとして一部に使われることが多いです。 |
| 珪藻土クロス | 珪藻土から作られる壁紙です。壁紙ながら塗り壁のような質を出すことができます。調湿・消臭効果があります。 |
| 無機質クロス | 土やガラス繊維などの無機質から作られる壁紙です。一般住宅にはあまり使われませんが、不燃材料を使っているので耐火性に優れています。 |
ちなみに、壁紙には「量産品」と「1000番台」の2つのグレードがあります。量産品は安価で1000番台は比較的高価です。1000番台の壁紙は定価が1000円/mなのでこのように呼ばれています。賃貸住宅には量産品、戸建てや分譲マンションには1000番台が使われることが多いです。
機能から選ぶ
消臭などの機能が付いている壁紙を「機能性壁紙」と呼びます。機能が付いていない壁紙と比べると費用は高めですが、お子さんやペットなどがいるご家庭は機能性で選ぶのもおすすめです。
| 機能性 | 概要 |
|---|---|
| 汚れにくい壁紙 | フィルムを表面にコーティングすることにより、汚れを落としやすくしている壁紙です。お子さんの落書きやキズ防止にも効果的です。 |
| カビや結露を抑える壁紙 | 吸水性ポリマーを含ませることで湿気を吸収し、乾燥時に放出する働きをするタイプもあります。 |
| 消臭できる壁紙 | 壁紙の表面に消臭剤を施すことで生活臭やタバコ臭、ペット臭を防ぎます。 |
| アレル物質の働きを防ぐ壁紙 | 表面に薬剤を施すことでダニや花粉などのアレル物質を抑制します。 |
| 抗菌効果のある壁紙 | 壁紙表面に付着したウイルスや菌の働きを抑制する効果があります。細菌の増殖も防ぐことが可能です。 |
| 省エネ効果のある壁紙 | 電球の光を反射・拡散することで、より明るいお部屋にできます。 |
色から選ぶ
壁紙は部屋の雰囲気だけでなく、視覚効果ももたらします。
- 暖色系:進出色ともいい、手前に迫っているように感じさせます。
- 寒色系:後退色ともいい、奥行があるように見せる効果があります。
赤やオレンジ、黄色などの暖かみを感じさせる色は暖色系に分類されます。また青や緑などは寒色系に分類されます。この2種類の色を同じ壁に使うと、暖色系は狭く感じさせ、寒色系は奥行を感じさせるため広く見せる効果があります。
他にも、緑だとリラックス効果があったり、赤は食欲増進などの効果があるとされています。このように色の効果で壁紙を選ぶのも、壁紙選びの方法の一つです。
また壁紙の色を決めるときに、パンフレットなどで小さな写真から色を決めることもあると思いますが、「面積効果」によって実際に貼ってみるとイメージよりも淡く感じることがあります。
面積効果とは面積が大きいほど色が明るく見える現象です。パンフレットやサンプルの大きさは4cm×4cmであったり、6cm×6cmと小さくなっています。サンプルで良い色だと思っても、実際に部屋に貼ってみると明るくなるという現象が起きる場合があるのです。
面積効果の影響を避けるために、良い色を選んだらA4サイズのサンプルをもらうことをおすすめします。また、実際に自然光で明るさをみたり、1m以上離れた場所から壁紙を見てみるとイメージが湧きやすくなります。
壁紙張替の費用
作業費を含めた壁紙張替の費用相場は1,000円/㎡~1,500円/㎡です。壁紙の費用は壁の面積によってかかる金額が変わってくるので、実際に現場を見てもらって見積もりを出してもらうのが確実です。
またリフォーム業者によって、壁紙張替の費用が「1平米(㎡)あたり」や「1mあたり」と記載に違いがある場合があります。1平米(㎡)だと1m四方あたりの価格ですが、1mあたりだと幅が明記されていません。
壁紙をメートル単位で販売している場合、幅は0.9mになっています。
壁紙はロール状になっており、メートル単位での販売だと必要な分だけカットするという販売方法です。
そのため、例えば同じ20平米(㎡)でも以下のように価格に違いが出てくる場合があります。
| 【20平米の壁に壁紙を貼る場合】 | 計算式 | かかる費用 |
|---|---|---|
| 1平米(㎡)あたり1,000円 | 1,000円×20平米(㎡) | 2万円 |
| 1mあたり1,000円 | 1,000円×20m+1,000円×2m (2mは幅の不足分0.1m×20mより) |
2万2,000円 |
同じような値段だと錯覚しやすいですが、壁紙の販売価格の表記には注意するようにしましょう。
壁紙張替のDIYでよくある失敗
壁紙の張替はDIYで行うことができますが、せっかく手間をかけて施工しても慣れない作業で失敗してしまうこともあります。よくあるのは以下の失敗です。
シワができる
壁紙が折りたたまれていたときのシワなどは、接着剤が乾いたころには無くなっていることがほとんどです。しかし、貼るときに十分に空気を抜ききれずにシワになってしまうと後から修正するのは困難です。
壁紙にシワができているのは、内部に空気が入っているのが原因ですが、カッターで少し切り込みを入れて空気を抜くことができても平らにはできません。
また貼るときはきれいでも、湿気の多い場所だと壁紙が湿気を吸って糊がゆるくなることで壁紙が波うったりすることがあります。場所に適切な壁紙を選ぶことも重要なポイントなので、シワを避けるためには専門の業者に依頼するのがおすすめです。
柄がずれる
柄のある壁紙を無地と同じように貼ってしまうと、1枚目と2枚目で柄がずれてしまうことがあります。柄の壁紙は等間隔で同じパターンがプリントされているので、そのパターンに合わせて貼れば柄がずれてしまうことはありません。
この同じパターンが印刷されるまでの長さをリピートといいますが、柄の壁紙を施工する場合は、事前にリピートの長さを確認してその長さ分を余分に用意する必要があります。
賃貸は契約書を確認しよう
賃貸住宅の場合、基本的に勝手に壁紙を張り替えることはできません。賃貸契約書には多くの場合、壁紙や床材の張替が禁止されていることが多いです。
どうしても張替を行いたい場合は、まず管理会社や大家さんに確認しましょう。確認するときは以下の点を伝えることが必要です。
- どのくらいの面積を変えるのか
- どのような壁紙にするのか
- 退去時は元に戻す必要があるか
確認した場合、やり取りの履歴を書面に残しておくと退去時のトラブルを避けることができます。
塗装するという選択肢も
内装で壁をリフォームする場合、壁紙の張替を行うほかに壁を塗装するという方法もあります。
| 壁を塗装するメリット | デメリット |
|---|---|
| ・壁紙では出せない質感を出せる ・複数の色を混ぜて自分好みの色を作れる ・壁紙のように廃材が大量に出ない ・塗りなおしができる |
・独特の臭いがある ・乾くまでに時間がかかる ・油性だと気化したときに体調不良を及ぼすものもある ・キズや擦れに弱い ・壁紙と比べて費用が高い |
壁の塗装は壁紙のように色や質が決められていないので、自由度が高いのが特徴です。塗料もただ単にペンキではなく、黒板塗料やスケッチペイント、マグネット塗料などバラエティ豊かです。スケッチペイントは塗るとホワイトボードのように使用でき、マグネット塗料は壁に画びょうなどを使わずにメモなどを貼り付けることができます。
しかし量産されている壁紙と比べて費用が高い傾向があります。また作業が1日で終わったとしても乾くまでには3~4日かかることもあり、その手間から塗装をしている業者は少ないです。
施工料金の高さから部屋全体ではなく一部のみを塗装にすることもあります。壁の塗装にはメリット・デメリットありますが、予算と相談しつつ一部を塗装にするという選択もよいでしょう。
まとめ
壁紙の張替はDIYだと手間がかかるほか、失敗する可能性もあります。仕上がりを重視するなら業者に依頼するのが確実です。また壁紙にも様々な種類があり、場所によって適切なものも異なります。ある程度どのような空間にするのかイメージが湧いたら、一度業者に相談してもよいでしょう。